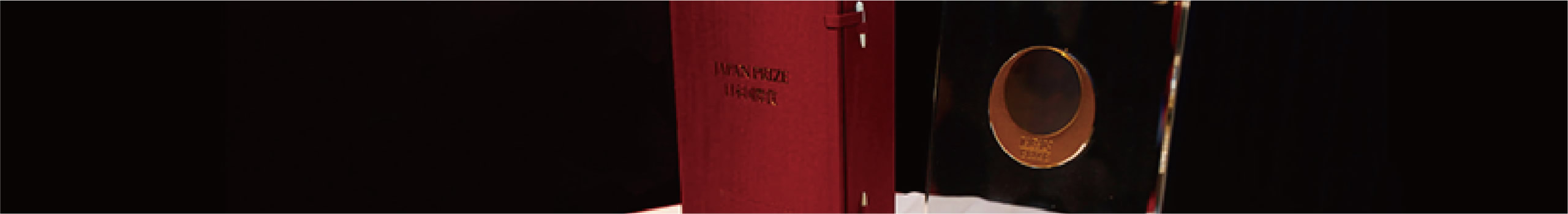
分野検討委員会とは、国際科学技術財団内に設けられた委員会です。翌々年の日本国際賞の授賞対象となる2分野を選定し、毎年11月に発表しています。また、財団に登録された世界16,000人以上の推薦人(著名な学者・研究者)にジャパンプライズWEB推薦システムを通じて受賞候補者の推薦を求めています。
| 委員長 | 宮園 浩平 | 東京大学大学院医学系研究科 客員教授 |
|---|---|---|
| 副委員長 | 橋本 和仁 | 国立研究開発法人科学技術振興機構 理事長 |
| 委員 | 新井 洋由 | 東京大学名誉教授 帝京大学 教授・副学長 東京大学大学院医学系研究科 客員研究員 |
| 五十嵐 仁一 | 公益社団法人日本工学アカデミー 副会長 元ENEOS総研株式会社 代表取締役社長 |
|
| 上田 修功 | 国立研究開発法人理化学研究所 革新知能統合研究センター 副センター長 NTTコミュニケーション科学基礎研究所 リサーチプロフェッサー(客員フェロー) |
|
| 沖 大幹 | 東京大学大学院工学系研究科 教授 | |
| 倉永 英里奈 | 京都大学大学院薬学研究科 教授 東北大学大学院生命科学研究科 教授 |
|
| 黒田 忠広 | 東京大学特別教授室 特別教授 熊本県立大学 理事長 |
|
| 堤 伸浩 | 東京大学 特命教授 | |
| 仲野 徹 | 大阪大学名誉教授 | |
| 波多野 睦子 | 東京科学大学 理事・副学長 | |
| 宝野 和博 | 国立研究開発法人物質・材料研究機構 (NIMS) 理事長 | |
| 元村 有希子 | 同志社大学生命医科学部 特別客員教授 | |
| 吉田 稔 | 国立研究開発法人理化学研究所 理事 東京大学特別教授室 特別教授 東京大学名誉教授 |
(役職は2025年11月授賞対象分野発表時、敬称略、五十音順)
| 「物理、化学、情報、工学」領域 |
|---|
| 授賞対象分野:「資源、エネルギー、環境、社会基盤」 |
|
(背景、選択理由) 科学技術は、私たちの生活圏と自由な時間を拡大し、あわせて自然災害による被害を減らしてきました。しかし、未だに貧困や欠乏の恐怖から自由ではない人々もいます。また、人口増加と人間活動の拡大による気候変動の悪影響や生物多様性減少の深刻化、資源の偏在等に伴う国際情勢の悪化などによって、平和のうちに生存する権利が脅かされています。 そのため、カーボンニュートラルな社会や循環型経済、ネイチャーポジティブなどの実現による地球規模課題の解決に期待が寄せられています。それには、非従来型を含むエネルギー資源や鉱物資源、水資源、物質循環にかかわる画期的な要素技術の開発と、全体の効率や信頼性の向上が不可欠です。さらに地震や豪雨洪水といった自然災害のリスク軽減に資する先端的な観測や予測も必要です。 また、すべての人々のウェルビーイングに資する、持続可能な社会への転換を促進するには、都市や農村における新たな居住・交通システムのデザインや、人間の行動選択やコミュニケーションと信頼醸成などの理解、それらを活かした安全で心豊かに暮らせる次世代型社会システムの構築が重要です。 (対象とする業績) 2027年の日本国際賞は、「資源、エネルギー、環境、社会基盤」の分野において飛躍的な科学技術の創造・革新・普及をもたらし、それらを通して社会課題を解決し平和で持続可能な社会の構築に大きく貢献する業績を対象とします。 |
| 「生命、農学、医学、薬学」領域 |
| 授賞対象分野:「医学、薬学」 |
|
(背景、選択理由) 近年、医学、薬学領域は飛躍的な発展を遂げ、かつて克服が困難であった疾患の治療や健康寿命の延伸に大きく寄与しています。分子・細胞レベルでの生命現象の理解は深化し、その知見は、ゲノム情報を活用する医療、遺伝子・細胞療法、次世代ワクチン、ドラッグデリバリーシステム、イメージング技術など、革新的な治療・診断法へと結実してきています。さらに、オミックス解析やシングルセル解析など疾患の発症や進行を精緻に解析する基盤技術や先端的な技術を応用した新たな治療様式(モダリティー)も急速に進歩し、医療の概念そのものを変容させつつあります。また、膨大な医療・生体情報を活用したデータ駆動型研究や、AIなど情報科学との融合も加速し、疾患メカニズムの解明から予後予測、個別化医療の実現に至る新たな道が切り拓かれています。 今後は、医学、薬学の学術的基盤に加え、情報科学、材料科学などの理工学分野とのさらなる連携から新たな発想や技術の展開が期待されており、こうした多様なアプローチの成果は人類の健康と福祉に大きな貢献が見込まれます。 (対象とする業績) 2027年の日本国際賞では、「医学、薬学」分野において、科学技術の著しい進展を先導し、疾病の機序解明、予防、診断、治療、さらには予後予測の革新により、人類の健康増進と社会の発展に寄与した、またはその成果の実現が見込まれる顕著な業績を顕彰の対象といたします。 |
日本国際賞授賞対象分野は、2授賞領域ごとに、以下の通り決定いたしました。
これらの授賞対象分野は基本的に3年の周期で循環します。
毎年、日本国際賞分野検討委員会から向こう3年間の授賞対象分野が発表されます。
「物理、化学、情報、工学」領域 |
「生命、農学、医学、薬学」領域 |
|
|---|---|---|
授賞対象分野 |
授賞対象年 |
授賞対象分野 |
資源、エネルギー、環境、社会基盤 |
2027年 |
医学、薬学 |
物質・材料、生産 |
2028年 |
生物生産、生態・環境 |
エレクトロニクス、情報、通信 |
2029年 |
生命科学 |