
ハーバード大学コンピュータサイエンス 教授

大阪大学先端モダリティ・ドラッグデリバリーシステム研究センター 特任教授

テキサス大学サウスウェスタン・メディカルセンター 教授
受賞記念講演会
「III-V族化合物半導体デバイスのための有機金属気相成長法の開発」
ラッセル・ディーン・デュプイ 博士
「持続可能な未来に欠かせないオーシャン・ポジティブ・エコノミー」
カルロス・M・ドゥアルテ 博士





ジョージア工科大学 教授

アブドラ王立科学技術大学生物環境理工学部 特別教授
受賞記念講演会
「Reflections on many years of trying to understand atmospheric motion」
ブライアン・ホスキンス 博士
「Encounters with atmospheric gravity waves and teleconnection patterns」
ジョン・ウォーレス 博士
「Organ Physiology and its Transcriptional Underpinning」
ロナルド・エバンス 博士



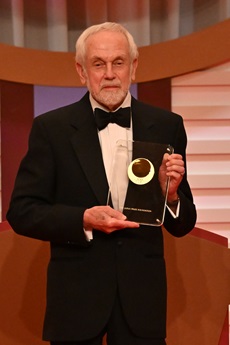



レディング大学気象学科 教授

ワシントン大学大気科学科 名誉教授

ソーク研究所遺伝子発現研究室 教授






受賞記念講演会
「半導体レーザー励起EDFAの発明と光ファイバーが創るICTの未来」中沢正隆 博士
「半導体レーザ励起光増幅器の開発を中心とする光ファイバ網の長距離大容量化」萩本和男 氏
「Optogenetics: Causes, Connections, Mechanisms」ゲロ・ミーゼンベック博士
「The inner workings of channelrhodopsins and nervous systems」カール・ダイセロス 博士





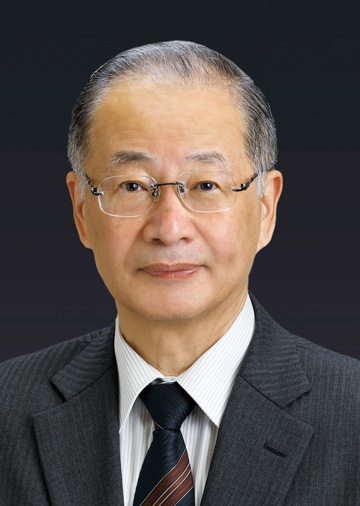
東北大学 卓越教授(DP)/特任教授

国立研究開発法人情報通信研究機構 主席研究員

オックスフォード大学 神経回路・行動学研究所 ウェインフリート生理学教授

スタンフォード大学医学部 バイオエンジニアリング学科・精神医学学科、ハワード・ヒューズ医学研究所 教授